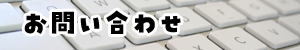学校長挨拶
『興味深い学びを』
梓川高等学校ホームページにアクセスしていただきありがとうございます。
本校はアルピコ交通上高地線沿線にある松本市西部地域唯一の高校です。
正門から徒歩3分の最寄り駅である下島駅の由来となった「下島(しもじま)」は、下島スイカの名前で全国に名前を知られる地籍です。学校は北アルプスから延びる里山に端を発する扇状地と、北アルプス槍ヶ岳に源を発する清流梓川に挟まれた河岸段丘上に位置しています。もともと明治43年(1910年)に「南安南部農蚕学校」として開校し、その後「東筑摩西部農学校」を経て、昭和55年(1980年)3月まで農業科を置いていた校内には、広大な敷地内に四季折々の美しさを醸し出す木々や草花に囲まれた自然豊かな学習環境が整っています。その後、全日制普通科単科高校として歩みを重ね現在に至っています。創立115年を迎え、14,000名を超える卒業生が、地元を始めとし各界で活躍しています。
在校生は、地元の中学をはじめ、松本平の中南部全域から通学しています。渕東なぎさをイメージキャラクターとする上高地線を使って松本駅から約20分で登校する生徒や、松本市中心部からは高低差が小さいなだらかな道のりを自転車で約30分かけて通学している生徒も見られます。昨年度より、生徒たちと行政との交流を通じ隣接する山形村・朝日村から梓川高校まで直通の地域連携バス(朝1本、夕方2本)も実現し生徒の足となってくれています。
地域連携バスに代表されるように、本校の生徒と地域との交流は、定期的に姿かたちを変え実施されています。コロナ禍以前(総合的な探究の学習実施以前)には、波田地区の満蒙開拓の歴史を広く子どもたちに受け継いでいってもらうための紙芝居を当時のことを記憶している方々や同地区の方々と作成しました。また波田中学校や地域住民と一緒に地域や高校生活について語り合うKAWAトークを本校生徒会が主催となり続けています。2年前からは、松本市とコラボレーションしながら市政と高校生が関わるつながりが生まれ、昨年度、松本市議員の皆さんと探究活動の野外研究を一緒に進めるなどの成果を生んでいます。
探究的な学びだけではありません。生徒の進路選択実現のため、継続的な基礎力定着に向けても取り組でいます。毎日の午前中のショートホームルームの一部を使って基礎的な問題から進学・就職に向けた応用問題まで取り組む時間を確保し、小さな時間の積み重ねが学力アップに繋がる経験を積んでいます。
2年生になると、自分の進路実現に向け「3つのコース;【教養コース】・【福祉・こどもコース】・【情報ビジネスコース】」に分かれることで内容を深めた専門科目を学ぶこととなります。とくに【福祉・こどもコース】では、【情報ビジネスコース】では。普通科でありながら通常普通科で学べない科目を学習することで、早めの実践に向けた学びを実現しています。
基礎から応用、学校内外の交流、普通の普通科にはない学びに興味を持った方は、一度、梓川高校を訪れてみてください。
長野県梓川高等学校長 西林 昭隆
本校にまつわる名物(?)
- 『樹木』
- 敷地内には70種260本を超える樹木が生い茂り、その中には日本において希少なものもあります。校門脇と中庭にある「魯桃桜(ろとう桜)」はその代表です。
他には、「メタセコイア」の大木、「オウシュウアカマツ」、また創立90周年を記念し植えられた「梓の木(キササゲ)」がテニスコートの南側・道路沿いに3本あります。「梓の木」は固くしなやかなので、梓弓として、また版木として使われたと言われています。(本を出版することを上梓するというのはこれが語源だそうです。)
他にも、ヒマラヤスギ、イチョウ、桜など、多くの大樹に本校キャンパスは囲まれています。 - 『梓水農魂』
- 校門脇に御岳火山の輝石安山岩の大きな自然石に、上條信山先生による書が刻まれています。
これは本校創立70周年の年、昭和55年(1980年)に本校の農業科が閉科された記念に建立されたものです。校長室にはその元となった書が掲げられています。 - 『柱時計』
- 校長室の南壁の大きな柱時計。「南安南部農蚕学校第十六回卒業生寄贈」で、大正15年(1926年)3月23日より時を刻み始め、今年で94年になります。
当時たいへん高価な物品だったと思われ、卒業生の母校愛を感じます。故障したこともあったようですが、同窓会の皆さんに修理していただき今も現役です。
ちなみに週1回ゼンマイを巻くのが私の仕事です。 - 『雲山大澤』
- 郷原古統先生の画が校長室の西壁一面に大きく掲げられています。
昭和36年(1961年)の卒業生が地元在住の老画家に制作を依頼。その熱意に感じた画家が4年の歳月をかけて、蝶ヶ岳の山頂から梓川渓谷を隔てて穂高連峰を望む壮大な景色を描き、本校創立50周年の昭和39年(1964年)に寄贈された大作(縦1m21cm 横2m45cm)です。
本校の作品はおそらく絶筆と思われます。 - 『校歌原稿』
- 作詞者である詩人・作家の佐藤春夫の直筆原稿が校長室に展示されています。手書き楽譜(作曲者 中田喜直)は残念ながら誰が書いたかわかりません。
本校の校歌は、生徒の「校歌を歌いたい」という願いに動かされ、昭和31年(1956年)に制定されたそうです。
それに応える詩人の思いがブルーブラックインクの力強い筆跡に現れています。 - 『熱誠愛』
- 東筑摩西部農学校初代校長高安三郎先生の信条としていた校訓の木製の額が校長室にどっしりと置かれています。
これは西農下島修練道場に昭和18年(1943年)から掲げられていたものです。 - 『下島橋』
- 「梓川村史」に次のように記載されています。
「梓川高等学校の新校舎建築に伴って、南安曇群下より通学する生徒の通学路として昭和25年(1950年)に架けられた。長さは132m幅員2.6mの木橋であった。この工事費は学校建築費の内から支出された。橋の建設費は当初130万円で計画されたが、工事着工後梓川の増水により工事が中断され、また橋脚が流出するなど災害のため工事が遅れ工事費が増額された。橋は木橋で…(中略)その後もたびたび災害を受け通行止めとなった。その後下島橋架け替え促進期成同盟が発足し関係官庁に陳情を行い、(中略)平成2年(1990年)10月竣工した。橋は旧橋の下流19mの位置に長さ213.7m、幅員9.75mのポストテンションPC単純T桁橋で歩道も設置された。」
注目すべきは、「生徒の通学路として架けられた」という点です。生徒のために橋を架けた。しかも災害で流出するたびに、当時の梓川村と波田村(町)が予算を出し合って補修を繰り返していたことが記されています。県下の高校で橋まで作ってもらった学校はあまり聞きません。今から70年前の地域住民の思いにあらためて頭が下がります。
時は移り、波田も梓川も松本市となりました。『下島橋』の果たす役割も大きく変わったことは確かです。しかし、『下島橋』は今も梓川高校生の通学する姿を見守り続けていてくれます。