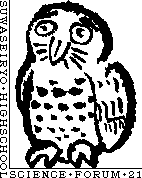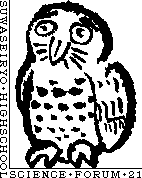|
1.はじめに
・諏訪は祖母の郷里でよく虫取りにきた。
・日本列島の構造上長野県はユニークな位置を占める。→よく観察すると自分の住んでいる地域が見えてくる。
2.個性とは
・個性は遺伝子的に最初から与えられている。
・「私は私」と自分は変わらないものと思っている人が多いが、人間は変わるものである。分子・原子のレベルでもどんどん変わっているし、考えていることも変わっていく。
・普遍的な論理には個性などない。→変わらないものは言葉(コミュニケーション)などの情報である。(万物流転・・・この言葉自体も変わらず真実である)
3.「学ぶ」・「知る」ということ
・「知る」→人が変わるということ
・「学んで」人間が変わると、行動に表れ「現実」になる。
・授業が退屈な人にとっては、その授業は現実ではない。
・教育とは人が変わらなければならない。
4.脳
・脳に五感を通して入力し、筋肉を通して出力する。
・いくら入力しても、出力をしなくては意味がない。脳の仕事は出力と入力のサイクルを繰り返すことである(体を使うことがまた考えることにつながる)。戦後の教育は入力に頼りすぎていた。いくら入力しても出力がなくては意味がない。文武両道とは入力(文)して出力(武)することである(知行合一もまた同じ)。学校では出力、入力ともに大切である。
5.質問
Q:小さい頃は何に興味を持っていたか?
A:休みの日は魚や虫を捕っていた。
Q:なぜ解剖学に興味を持ったか?
A:敗戦(小2)により価値観が変わり、確かなもの(普遍性)が欲しかったから。
|