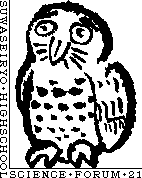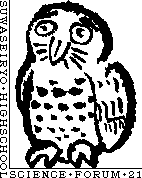| 日 時 |
2004年1月24日(土) 9時40分〜12時 |
| 場 所 |
諏訪市文化センター
(諏訪市湖岸通り5-12-18) |
| 対 象 |
本校生徒1・2年生、 保護者・一般の方約 50名 |
| 講 師 |
講師
増澤敏行先生(名古屋大学教授)
濱健夫先生(筑波大学助教授)
講師・コーディネーター
花里孝幸先生(信州大学教授) |
| テーマ |
シンポジウム「諏訪湖から外洋まで〜水環境の比較から水質汚濁問題を考える」 |
| 内 容 |
花里:今日は進行役を務めます。私たちの専門は湖などの水系であります。水域の中で無機物や有機物の循環を研究しています。まず、自己紹介をかねて、先生方の専門を紹介してください。
増澤:岡谷の今居出身で69回生です。京大から名古屋大へきました。元素から物質循環を見ています。昨年度の清陵祭で交流会を持ちました。その時に、天文部の太陽黒点観測がまだ続いていて、すごいと思いました。今日は、一つでもおもしろいものを見つけて欲しいと思います。
濱: 私も清陵出身です。当時は生物部で、諏訪湖に来ていました。私は海の物質循環を専門にしていますが、清陵で生物部に入っていたことが、この分野に進んだ理由の一つとなっています。生物は孤立して生きているものは一つもなく、水の中でも物質を取り入れて老廃物を水中に出して生きている。プランクトンも同じであり、生物と環境は一体のものとなっている。そのことを物質循環といい、それを研究し、水質汚濁について考えています。
花里:私は長野県出身ではないですが、今は諏訪湖のほとりにある信州大学の研究所にいます。湖の生態学が専門ですが、特にプランクトン、その中でもミジンコが専門です。ゾウミジンコが諏訪湖にはたくさんいます。大きさが0.5mmになります。他にもたくさんのミジンコがいます。さらに植物プランクトンも諏訪湖には生息していて、食物連鎖によってつながっています。植物プランクトン→ミジンコ→ワカサギ→ブラックバスなどの連鎖がある。相互に結びついて生物間相互作用と呼ばれる。私はそうした作用の中での生物の種について研究しています。
花里:諏訪湖は長野県で一番大きく、しかも面積の割には浅い湖です。そして、アオコが出ることで有名です。ミクロキスティスと呼ばれる植物プランクトンが群体をなし、粘液を出して湖の上に浮いて風に流されます。このアオコが水質汚濁を引き起こしているのです。昔の諏訪湖は非常にきれいでしたが、1960年代に汚れが深刻化していきました。諏訪湖の透明度を見てみると、1970年代は平均40cmで最もひどかった。1979年に下水処理場ができると70cmとなりその効果が出たように見えました。しかし、それ以降下水処理が進んだにもかかわらず、湖の浄化はあまり進みませんでした。やがて、1990年代になって、アオコが少なくなって透明度も1mを超えられるようになりました。近年の透明度の回復は、やっぱり諏訪湖の下水処理の普及が原因で浄化が進んでいると思われます。現在は下水の普及率は90%を超えています。湖の浄化がなかなか進まない全国の現状の中で、唯一きれいになりつつある諏訪湖は注目されています。なぜ浄化が進んだのかという原因を考えてみますと、下水処理場が作られて20年たち、ようやく効果が出てきたということです。要するに湖の浄化には時間がかかるのです。昨年の新聞には、諏訪湖の水質が、県内ワースト1を脱するという記事がありました。アオコが減ると、水草が増え、エビなどの水生昆虫が増えるということになり、生態系の変化が見られます。このアオコによる水質汚濁は富栄養化ということなので、その専門家の濱先生に富栄養化についての話をしてもらいます。
濱: 海洋表面におけるクロロフィル(植物)の分布の図です。北の海に多いことがわかります。冷たい海で多いのはなぜかというと栄養分の多さと一致しているのです。陸の影響です。植物プランクトン(アオコ)は水の中のCO2や窒素・リン(栄養塩)を利用しながら生育していきます。窒素・リンが植物プランクトンや有機物の増加につながるのです。この栄養塩が豊かになることを富栄養化といい、特に湖で使用される言葉です。富栄養化は貧栄養湖が周囲の自然の中から物質を取り込んでさまざまな生物が生きられるようになるときに使われる言葉だが、諏訪湖は人為的富栄養化の例で、周辺の人間活動の結果汚れてしまったということになります。人為的富栄養化の場合は急速に富栄養化が進みます。窒素・リンが良くないということではなく、それが植物プランクトンを増やすことが問題で、これが増えると透明度が悪くなります。この透明度やCOD(科学的酸素要求量)というものが汚濁の指標となります。窒素・リンが植物プランクトンを増やし、その結果有機物が増え、酸素が消費され酸素の少ない湖となり、透明度が低下します。花里先生の先ほどの話である1970年頃の諏訪湖がまさにこれだったと思います。
花里:海では富栄養化の問題はどうなっているでしょうか。増澤先生どうですか。
増澤:はい、では内域の伊勢湾・三河湾から富栄養化を考えてみます。この湾は人口900万を抱える流域を持つ木曽川などが流れ込み、富栄養化が進み植物プランクトンが増加しています。2001年7月末には海が、名古屋湾はこげ茶色、三河湾の奥は緑色、伊勢湾中央は薄緑色、伊勢湾の外洋では青色できれいでした。色から見た伊勢湾の中の様子がわかります(写真)。2001年にも赤潮が発生している。これが死んで下に沈むと酸素が消化されてしまいます。また、苦塩も発生し問題となります。赤潮は三河湾では1960年代から見られるようになり、透明度も下がりました。2mくらいです。1970年代から80年代にかけて赤潮発生日数が急増しています。三河湾の埋め立てが進み、その結果ではないかと考えられます。
花里:(ここまでのまとめ)海でも湖でも窒素・リンが原因で富栄養化が起こり、同じような現象が起こっていることがわかります。伊勢湾の透明度は3mなのに対して外洋では30mあります。日本で一番きれいな摩周湖の透明度は30〜40mあります。しかし、富栄養化は水が汚れるという悪い一面だけではありません。富栄養化が進むと植物プランクトンが増え、それをえさとする動物プランクトン(ミジンコ)も増え、またそれを食べる魚も増え、漁獲量も増えるということになります。諏訪湖ではアオコが大発生して一番汚れた70年代に漁獲量がピークを迎えています。富栄養化は漁業にはプラスとなるのです。逆に水質が良くなるということは生物が減るということでもあります。実際に、昔大発生していた諏訪湖のユスリカが減ってきています。1999年からアオコが減少するが、その直前の1998年秋からユスリカが減り始めました。昔は1m2あたり5000匹いたユスリカの幼虫が、今は1m2あたり200匹になっています。そして、ユスリカ(特にアカムシユスリカ)の幼虫を食べているワカサギが小さくなってきています。浄化の結果生物が減るから漁業にはマイナスとなり、人間の生活にも影響が出ます。
濱: 霞ヶ浦にもアオコがあったが今は減少しています。それに応じて漁獲量も減少しています。霞ヶ浦では窒素・リンの量が変わらないので植物プランクトンの量は減少していなくてその原因は不明です。将来の食糧難を考えて海での漁獲量を増やそうと海洋施肥計画というものがあります。アンモニアを海にまきプランクトンを増やし水産資源量を上げようとするのです。アメリカ合衆国では自然科学的検証なしにそのプロセスの特許がとられています。この計画はCO2の大気中の増加の問題に関係があるとされています。人間の放出するCO2の30〜40%は大洋が吸収し、一部が深海にC(炭素)隔離されます。炭素の循環を利用して地球温暖化を抑える可能性も考えられています。
増澤:海では暖かい赤道付近よりも、北極や南極に近い海域の方が富栄養化が高い。陸上とは逆です。その原因はミネラルなどと呼ばれる金属元素の濃度が関係しているのではないかと考えらています。そこでアメリカ合衆国は赤道付近の海域で鉄まき実験を行いました。その後植物プランクトンの増加が見られました。これが海洋資源増加のために効果があることが期待されています。しかし、貧酸素水塊の形成や亜酸化窒素・メタンなどの温室効果ガスの発生などが起こり環境のことを考えると人為的に行うことには問題があります。
花里:人間にとっては植物プランクトンの増加はよいこともあります。みなさんも、富栄養化、水質汚濁という言葉の理解が深まったのではないかと思います。環境問題は複雑であり、一方的な見方ではなく総合的に考えることが大切です。人為的に生態系を変えることには慎重であるべきです。富栄養化は陸と海、湖で違い、海でも赤道域、寒海域で違います。しかし共通面もあります。個別的な面と共通な面があり、それをつきつめていくと見えてくるものがあります。最後に、諏訪湖の将来に対する期待についてお話ししてください。
増澤:釜口水門を見に行くと、アオコが見えずに喜ばしく思いました。水は我々に必須のもの、昔は諏訪湖の真ん中の飲料水を汲みに来ました。エビ・貝が住めるような諏訪湖を子孫に残せるよう期待します。
濱: 3万年以来の諏訪湖が50年前からの汚濁で劇的にかわりました。我々は、我々の利便性だけを考えてきました。たしかに水がきれいになれば魚の量は減ります。しかし、全体量は減るが、種類が増え多様な生態系になる可能性がある。諏訪湖は日本で唯一浄化の成果が見られた湖である。50年後の諏訪湖を見てみたい。
花里:私のような生態系の研究にたずさわるものが将来のあるべき姿を示さなくてはならないと思います。諏訪湖についてはもう少し浄化が進んでくれたらと思っています。今後浄化が進めば透明度が上がり貝や水草が復活し、そしてヤゴや水生昆虫が増えるでしょう。しかし諏訪湖は浅いので、底の汚れが上がることもあり簡単には浄化が進まないと思います。摩周湖のようには絶対にならないものの戦前位に戻る可能性は十分に考えられます。水質汚濁は悪いことだから浄化すればよいと考えることができますが、その後のことも考えなくてはいけません。たとえば、浄化が進めば魚の漁獲量は減ります。しかし、エビや貝など他のものが取れるようになります。環境問題は複雑で一面だけを考えればよいわけではありません。しかし、諏訪湖は富栄養化がまだ進んでいるから浄化は進めるべきであると思います。自分でものを考え、その上でいろいろな立場の人と話すことにより理解が深めあうことができます。ご静聴ありがとうございました。
---------------------------------
<生徒からの質問>
・魚の放流と環境の関係は?
花里:プランクトンは魚の影響を強く受けるので生態系は大きく影響を受けます。ただ、日本では昔から放流は行われてきて魚を増やしてきたということはあります。
濱: 海は湖よりもオープンなので放流の影響はほとんどありません。海底に障害物を置き、海流により海底の栄養を上層に上げより自然に近い方法で漁獲高を上げることも考えられています。
・海洋深層水飲料を飲んでも大丈夫か?
濱: 脱塩して商品化しているので普通の水とほとんどかわらない。ただ、生物量の少ないきれいな水なのでこれをどう活用していくかは今後の課題である。
増澤:1000mの深さで本当の深層水ではない。微量元素の影響はあるかもしれないが、害はほとんどないと思われます。
|