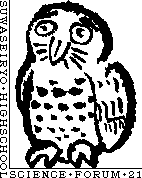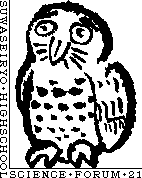|
Ⅰ.第一部
各先生方より講義があり、コーディネーターの方より簡単な質疑応答があった。
1.小宮山先生
・今、私がここにいるのは長い地球の歴史の帰結であり、天文学的偶然の帰結である。拒絶反応をはじめ、生命には不思議な能力が備わっている。子供の生命力はすごい。しかし白血病などわからないこともあり、その場合告知の問題がある。今は告知し、患者に信頼され治療し、死を迎えることが必要ではないか。
・大学の医学部は、医者を育てる、臨床、研究という三つの役割があると思うが。→教育、「良い医者」とは人間性・教養・コミュニケーション能力も含む課題探求能力も大切。
2.松田先生
・神経内科の紹介。神経疾患(パーキンソン病など)、膠原病などを扱っている。(アミドイローシスを例にとって)医療の進歩のめざましいものがある。しかしこうした新治療法は全員にできるわけではなく、医療には常に「おそれ」の気持ちをもって臨むことが大切である。最新の医療を使うには「人間性」が必要である。
・諏訪の個性とは→内にこもりがちになるので、世の中を広く見て欲しい。
3.大道先生
・新生病院の紹介。ホスピスの説明。
ホスピスとは、死ぬ前に最後に過ごすところ、希望があるところ、精神的・肉体的苦痛の緩和が専門(癌の痛みは簡単に取ることができる)。ホスピス医療の中心は痛みの緩和である。入院のみならず、在宅・通院もある。ホスピスに求められる二つのC。それはコミュニケーション能力とコーディネーション能力である。
・県内にホスピスは→4カ所、40床。
・平均入院期間は→まちまちだが約30日。
・なぜ信州大学へ、なぜホスピス医に→はじめは文系であり、科目の関係で。もともと放射線医であり、自分も痛みに弱いから。
4.吉永先生
・サイエンス・ライターの立場から
「死」と対比して「生きる」ことを考えると、「生きる」ことは健康であること。健康は身体的(フィジカル)に、精神的(メンタル)に、社会的(ソーシャル)にうまく機能していること。しかし、現在は、メンタルがフィジカルに吸収されて解釈され、ソーシャルまでがフィジカルに吸収されて考えられるようになり、物質一元論に進んでいるのではないか。すべてが科学的に扱われようになっているが、「思いはかる」ことが大切。生きていることの中に「死」がある。
・幅広く学ぶことの重要性について。
漠然としたジェネラリストでは意味がなく、スペシャリストであることは必要。歯車としてのスペシャリストでは解決できないことがあり、いろんなことに顔をつっこんで人間性を磨くことが必要である。
Ⅱ.第二部(シンポジウム)<敬称略>
飯島: 生徒から多くの質問をもらっています。まず、医師になって良かったこと、つらかったことをお願いします。
小宮山:小児科医として一番うれしいのは、治って数十年して健康な子供を連れて訪ねてきてくれること。健全な父、母になるということが本当の意味で健康になったということです。だから子供を連れてきてくれると本当にうれしい。つらいのはその逆です。
飯島: なぜ小児科医になられたのですか。
小宮山:子供が好きだったから。子供に注射という苦痛を与えるのがいやだったが、それを乗り越えた。
飯島: 松田先生はいかがですか。
松田: うれしかったこと、つらかったことは小宮山先生とほぼ同じです。一年目に心筋梗塞の患者さんとであったとき、患者の近くにいなくて先輩に怒られました。
それで近くにいたわけですが、その夜患者さんに不整脈が出ました。ずっと付き添っていたので助けられましたが。うれしかったです。つらかったのはやっぱり救えなかったとき。
飯島: 松田先生は、なぜ神経内科を選ばれたのですか。
松田: 脳はまだよくわからない分野で難病が多いといわれているところです。ひょっとすると解決できるかもしれない、そういうところに惹かれて第三内科つまり神経内科を選びました。
飯島: 大道先生はいかがですか
大道: 患者さんの痛みが取れて、笑って手を振って退院されていくとき。頑固な男性の表情が変わって、「ありがとう」といってくれるとき、そういうときがうれしいときです。治る人がたまたま来る場合がありますが、それがわかって助言をして、他の病院に行ってもらって治ったということもあったが、これもうれしかったです。治る見込みのある方は、ホスピスにきてはいけない人です。がんばって、がんばって、がんばりすぎているんだけれども、表情をみて疲れているなと思えるようなとき、どうケアしたらいいかがつらく思うときがある。
飯島: 吉永先生も周囲にはお医者さんが多いと思いますが、先生のみているお医者さんはどんな方々ですか。
吉永: 周囲にはたくさんいますが、みんな頭が良くて、性格がいいです。でもみていて大変だなと思うし、自分では医者になりたいと思わない。そして、最近学校のテストができるから医者になるという場合が出てきていると思う。非常に困ると思う。強いモチベーションをもった人が進むのはいいと思うが。以前山梨医科大学で、いい質問をする学生さんに会いました。先生方にどういう学生さんか聞いたところ、会社勤めを経験して医師を目指している学生さんだということでした。
飯島: 小宮山先生に伺いますが、最近いろいろな経験をして、途中から志を改め医学部を受け直す人が多い気がしますが、最近の傾向はどうですか。
小宮山:文科省の制度に学士編入制度があり、これによりしっかりとした目的意識を持って入ってくる学生が多くなってきている。
飯島: 若い生徒さんの質問に、先生方は「死」は怖くないですか、という質問があります。他にもいつかくる「死」をどのように考えますかとか、治らない病気の患者さんに告知する必要がありますか、するとしたらどのようになどがあります。小宮山先生いかがですか。
小宮山:死はやはり怖いです。難しい質問ですが、昔哲学を学んだとき「死を思うから生が成熟する」とありましたし、哲学的にはドイツのハイデッガーなど死を考えている哲学者ですか。また、入院患者さんの経験手記などもあってそれらを読むと、告知は必要な場合もあるが、その時と場合によるのだと思いますし、しかるべき時・場所・仕方などかなりのテクニックがいると思うし、配慮が必要だと思う。
飯島: 死の受容について、ホスピスの方はどうですか。
大道: ホスピスでも、死ばかり考えている人は想像されるほど多くはない。その人その人の死に対する考え方がある。死を考えていない人にはあまりそのことは話さない。考えている人にも少しずつ段階を踏んで、状況に応じて、患者さんに応じて考えていく必要がある。一度に話すようなことはしない。ケース・バイ・ケースである。
飯島: 告知について苦労したという臨床での経験はありますか、松田先生。
松田: 家族の了解などいくつかの指針は決められているが、告知は医者の技術に負うところが大きいと思う。だからかなりしっかりとした先生(うまく対応できる医師)でないと告知してはいけない。私もやっぱりやったことがない。かつて、一人画家の患者さんを思い出します。本人に告知して欲しいと頼まれましたが、結局いえなかった。後で家族の方に聞いたのですが、本人は察知していたらしかったです。
飯島: 吉永先生はどうですか。
吉永: 告知については賛成派です。自分は「死」は怖くはありませんが、痛みは怖いです。現実にそうなったらわからないが、告知はしなくてはいけない。そうでないと生きることが完結しない。ですがその受容までにはものすごい苦しみがあると思う。でもそれはやっぱりそれぞれの人の苦しみや苦痛の中でなされるもので、それがまたその人の人生そのものといえる。人によると思うので、先生方は大変だと思うが、個人的には賛成です。
飯島: 告知は難しい問題です。まとめると、その場や状況で考えるべき問題だといえそうです。さて、今度は医療技術の進み方は著しいものがあります。しかし、その結果、生命に対する考え方にきしみが出てきています。生まれる前に、赤ちゃんの(障害の)ことがわかってしまったり、脳死で生きながらえたり。そうした先端医療について聞きたいです。小宮山先生どうですか。
小宮山:生命科学、医療の進歩はすさまじい。次々と新しい技術が導入されている。しかし、こうした新しい技術は社会の中で育っていて、人間の尊厳が必要とされている。倫理的なreviewがしっかりとしなくてはいけない。哲学、倫理、宗教など多くの立場から考えることが大切である。私事だと、この医療技術の進歩について一ついいたいことがあります。それは抗生物質です。小児科の病気のほとんどは感染症のものです。そこでペニシリンなどの抗生物質ができたときには、小児科はもう必要ないといわれました。でもどうでしょうか。やがて抗生物質に打ち勝つ病気が出てきました。今度はもっと強い抗生物質を使用するといういたちごっこになってきました。有名な小池先生の著作によると、地球の歴史を1年とし、今が12月31日の除夜の鐘が鳴っているときとします。そうすると細菌は3月25日に誕生したことになります。人間の誕生は12月31日の午後7時30分頃の誕生になります。人間にとって細菌は大先輩となります。人間より進歩を積み重ねてきた細菌をやっつけるのはおこがましい。細菌はさっと体を変えて生きていこうとする。これからはやっつけるのではなく別の視点で考えていくべきであり、先端医療を考えていくべきである。
飯島: 吉永先生は、先端医療についてどうですか。
吉永: 医療の場合は病気の人対象だから良いかもしれないが。現代は茶髪、プチ整形を受け入れる土壌がある。さらに進めて脳の中に携帯電話のようなチップを埋め込むことができるようになればこれを受け入れる土壌があるといえる。こう考えると怖いという感じがする。ベーコンは「知は力なり」とかつて言ったが、この言葉をもう一度考えてみる必要がある。
飯島: 松田先生、何か付け加えることがあればお願いします。
松田: 筋肉だけがやせていく病気がある。筋肉がやせていけば呼吸ができない。昔はだからそこで終わったが、今は人工呼吸器をつけたりして生きられる。今ではそれで生きている方がいるのですが、その分家族にも負担がかかってきたりしているので、本人と家族の間での意見の一致が必要になってきていると思う。本人はもういいという人もいれば家族は生きながらえて欲しいという場合や、その逆もある。
飯島: それでは、高校生の若い方がいっぱいいますが、メッセージを一言ずつお願いします。
小宮山:努力を継続してください。何でこんなことができるのだろうかと思うことがあると思いますが、でもできることがあるのです。男子体操はだめだと思っていたが、最近世界体操選手権で日本選手が優勝しました。彼が文科省の遠山大臣を訪問して、努力して練習を続けて優勝できたと言っていました。大きな目標を持って努力を続けてください。
松田: 努力を継続することは同感です。そして、流されるなと言いたい。世の中にはさまざまな誘惑もあるが、苦しいけれどやりたいことのために突き進むことも大切です。校長室にもありましたが「千萬人吾往矣」の気概を持って欲しい。
大道: 高校の時の友人を大切にしよう。さらに進めて、いろいろな人と出会い、価値観の違いを受け入れようと言いたい。そうすれば今起こっている中東の問題もうまくいくと思う。そうしてバランス感覚も大切にして欲しい。
吉永: こんなに私語の少ないのは初めてである。また、熱心にメモをとっている生徒もいる。何も言うことがありません。聞いてくださった皆さんはすばらしい。失敗もあるだろうが自信を持って進んでください。本当にありがとう。
飯島: 皆さんが真剣に聞いてくださって、びっくりし、感謝しています。四人の先生の話を聞いてわかったと思うが「生きること、死ぬこと」は難しい問題です。告知を含めて難しい問題です。かくあるべきという答えはありません。よく考えて、自分なりの考えをもつことが大切です。そして、今日のフォーラムが、こうしたことを考え続けていく機会の一つとなればとと思います。今日はどうもありがとうございました。
|