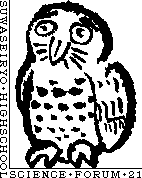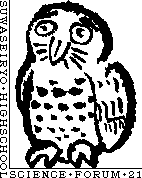|
1.医科学の歩み
医科学とは人間科学や生命科学に基盤を置いた応用科学であるとの立場から、人間科学が肉体に関する諸科学と心についての諸科学の基盤の上に、人文科学と社会科学を積み重ねた応用科学であるが故に、科学技術の進歩、社会科学や人文科学の影響を大変強く受けるのが特徴であるとされる。そこで例えば「死」をどのようにとらえるかについて、1人称の死ではなく柳田邦男氏の2.5人称の死すなわち死を悲しむ人に受け入れられるかどうかが問題であるとの考えを示され、さらに「死」を敗北ととらえるのではなく、死の方から人生をとらえ、現世においていかに生き最高のゴールとするかが大切であるとされた。
2.私の医科学への歩み
自分でしかできないオンリーワンを目指したのが医学部進学の動機であり、さらに「人が好き」というその根本にある考えも示された。研究生活への取り組みについては、徹底した研究への没入の姿勢、一方で1日2回の出勤による家庭人と医療人との両立など、先生の人柄が感じられるお話も聞くことができた。
3.歩みと思索から得られた研究哲学・人生哲学
我々に対して望むことを中心に語られた。まず、自分でなければできないオンリーワンの研究・人生を追求して欲しいということ、次に独創的研究のために徹底的な「思索」(考えること)を繰り返し、自己に厳しくかつ謙虚であることを忘れないこと、医科学研究者にとってチームがいかに重要であるかということなど、様々な例を示しながらまとめられた。
講演後の先生を囲む会には、意欲的な生徒が多数出席し、「死」(安楽死の問題にも触れられた)の問題や、「探し求める心」について、先生が苦労と思うこと、医科学の境界領域あるいは周辺科学との関係などについて、質疑応答が行われた。なお、先生が現在取り組まれているリンパ管の再生やガン細胞の転移メカニズムの研究についてもお話しいただいた。
|