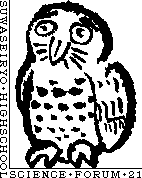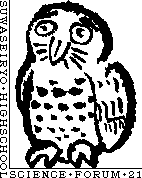| *サイエンスフォーラムは、一般の方も当日聴講できます。事前の申し込みは必要ありません。 |
| 日 時 |
平成17年9月16日(金) 第一部14時〜 第二部(講師を囲む会)15時45分〜
|
| 会 場 |
諏訪市文化センター |
| 講 師 |
一ノ瀬 俊明先生 (国立環境研究所地球環境研究センター主任研究員)
牛山 素行先生 (岩手県立大学総合政策学部助教授)
|
| 内 容 |
<一ノ瀬先生>
先生はまず、大学や研究機関に所属する学者という職業に対して憧れや夢をもっている生徒のみなさんには、今日の二人の話は、そのような夢を裏切るような内容かもしれない−と前置きをしてお話を始められた。すなわち、趣味と実益が結びついた、アカデミックな華やかな側面ばかりではない。むしろ、先生が現在携わっていらっしゃるのは、野外に出てデータを集め、分析を重ねる地味な研究活動であること。それは、古くは三沢勝衛先生など著名な先学を多数輩出している諏訪清陵高校の伝統であり、今なお同校にしっかりと息づいている分野であろうことを思うと何か因果を感ずると述べられた。
東大に進学されてからも、先生は必ずしも一直線に専攻を絞られたわけではなく、いくつかの進路変更をされた後、たどりついたのが後に先生のライフワークとなる都市工学の研究分野であった。−災害は突然人を殺すが、環境問題は真綿で首を絞めるようにじわじわと人を殺す−このような認識のもとに先生は研究を続けられ、東大大学院修士課程を終了後、農林水産省林野庁に採用され東京霞ヶ関勤務を経て、栃木県足尾町に営林署の治山事業所主任として赴任。その後東大研究室に戻り、助手として教鞭を執るかたわら博士号取得のための研究に励まれた。都市のエネルギー消費と都市の気候に関するテーマで博士号を取得し、現在の職場である国立環境研究所へ転勤となる。−との先生の現在に至るまでの略歴を話された。先生はその後、プロジェクターを用いて写真や図を示しながら、先生の研究分野の具体例を紹介してくださった。温暖化を防止するために、二酸化炭素をたくさん出さなくてすむ都市計画、街づくり。地域暖房の考え方。エネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出は、日本よりも急速に発展するアジアの大都市で重要であること。中国の環境問題。韓国ソウル市における清渓川復元工事による暑熱緩和効果。ドイツシュツットガルト市における「風の道」。一旦出てしまった大気汚染物質を市街地の風通しをよくすることで、速やかに吹き飛ばしてしまおうという考え方。これはまた、暑さの解消にも役立つ。先生は現在この「風の道」を生かした街づくりを長野市に実現できないかと気象観測を中心に研究を進めていらっしゃるとのことであった。最後に先生は、自身さまざまな紆余屈曲を経てたどりついた現在の研究、仕事であることを踏まえ、学生の皆さんは、自分の好きな分野の研究をしたければまた自分の好きな分野にかかわる仕事をしたければ、必ずしもそれと全く直結する学科に進学する必要はない。むしろ学生時代はあまり目先の損得を考えず、自分の本当に勉強したいことをのびのびやってほしいと締めくくられた。
<牛山先生>
先生は「私と自然災害研究」という演題により私たちに、急速かつ広域に突然作用する自然災害を見る目を示唆してくださった。まず、一口に災害と言っても実は2種類あるということ。disaster(災害)とhazard(外力、自然加害力)。だから、同じ現象が起きても人間がいなければdisasterにはなりえないのだという説明。特に自然災害を学んでいく上で大切になってくるのが、広い眼、長い眼。定量的、客観的・・・というようないわゆる思い込みや限られた見解を排した科学的な思考であるということ。人間は昔のことは忘れやすいが自然の振る舞いは大きくて長い。これまでにもわれわは、激しいさまざまな災害を経験し、にもかかわらずそれを忘れてきた。しかし、今回起こった程度の現象はこれからも確実に起こると思った方がいいということ。先生は、具体例としてフィールドワークから学ぶことの大切さをお話くださった。“今までこれほどの災害は経験したことはない”、“今回の災害で、犠牲者の大半はお年寄りであったから、お年寄りの救助体制を整えることが大切”などとまことしやかに聞こえてきた現場からの声。しかし、果たしてこれだけで片つけていいものか? 実際、現場に赴きフィールドワークを行うことで必ずしも人々のいうがままではなかった現実が見えてきた。確かに、土砂災害のお年寄りの犠牲者は多かったものの、洪水災害の犠牲者はむしろ通行中、移動中の65歳未満の犠牲者が多かったことが判明したのだ。だから、いくらお年寄りの救助体制を整えてもそれだけでは救えない多数の人がいることがわかったのだった。このように、先生は、災害に対しての実地調査の大切さを教えてくださった。そして、清陵の学生であった時、近くで台風が発生し、あわてて現場にとんで行き現場の写真を撮ったり、調べたりした貴重な体験をお話しされた。その場に行って、自分が心から気の毒だなあ、どうして災害が起こってしまったのだろうかとの素朴な思いが、実は現在の先生の研究姿勢の原体験ともなっているのではとのことであった。
最後に、学生に向けて。−研究者は、ハイリスク、ローリターンであること。人とうまくコミュニケーションができ、自力で問題設定及び解決ができる人は学者向きであると思われる。何をしている時が自分が一番身が入るか、素直に考えて見つけてください。と結ばれた。 |