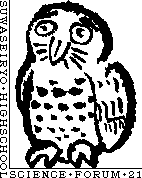
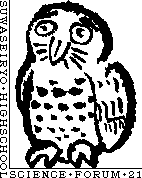 |
清陵サイエンスフォーラム21 | ||
| 〜未来をひらく知の誘い〜 | |||
| 生徒の知的探究心を喚起、自然科学の魅力を満喫させ、未来への夢や希望を大きく育むことを目指し、全国各地で活躍するトップクラスの研究者・技術者を招いて講演会やシンポジウム等を開催します。 | |||
| 第12回 「清陵サイエンスフォーラム21」 科学技術と社会 |
||||||||
|
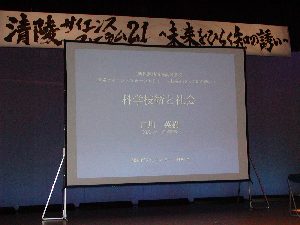 |
 |
|
| 演題「科学技術と社会」 | 白川 英樹 先生 | |
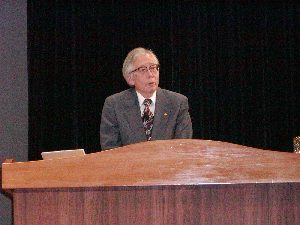 |
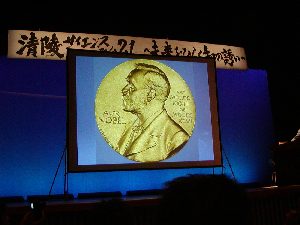 |
|
| ご講演の模様1 | ノーベル賞メダルのスライド | |
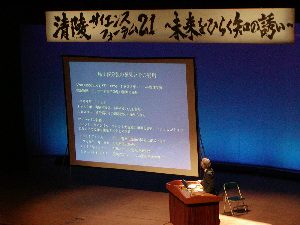 |
 |
|
| ご講演の模様2 | 拍手でご退席。ありがとうございました。 | |
| 清水ヶ丘便りでも一部報告していますvol.7(pdf 1.92MB)) | ||
| 講演の要旨と質疑応答 |
|
| 1.はじめに | |
| 「科学技術の役割と社会」「科学者技術者の社会に対する責任」「科学技術の発展を人々はどう受け取っているか」「日本の科学技術の政策とその結果」「科学研究費補助金」「大学の役割」等について話していきたい。 | |
| 2.感慨を新たにした メダルのデザイン | |
| 4年前にノーベル賞を受けたが、感慨を新たにしたのはそのメダルの裏に描かれたデザインだ。2人の女神が立っているが、左が「自然」という意味の名前を冠したラテン語のナトゥーラ、右が「科学」という意味のスケーンティアと呼ばれている。科学の女神は遠慮がちにベールを持ち上げているが、これはすなわち「自然をよりよく見るにはその内面にせまる」ということを意味しているのではないか。このデザインは物理学賞、化学賞だけのもので、「基礎科学」を意味している。 そこから科学の女神が、自然の女神のベールをあげたのは、「自然と共存するための知識を得る」「自然を知ろうとする知的好奇心」と解釈できる。 そこで認識してほしいことは、科学と技術は別のものであるということ。科学とは「知的好奇心を満足させ、心を豊かにするもの」、技術とは「健康を守り、生活を豊かにし、よりよい社会生活を守る」ということである。 ある統計のデータによると、自然と人間との関係に関して、「幸せになるためには自然と調和していかなければならない」と考える人がとても多いのだが、「科学」と「技術」の関係、そして「自然科学」と「人文・社会科学」の関係いずれも車の両輪のようなものだと思う。 |
|
| 3.21世紀は知の世紀 | |
| 20世紀は科学技術の世紀であったが、21世紀は知の世紀であってほしいと願っている。科学技術の発展によって、長寿を全うし、また物質的には豊かになってきたが、心はどうか。環境はどうか。富の偏在を加速させたが、南北問題の解決には寄与できなかった。つまり科学技術の発展により「功罪両面」がある。 |
|
| 4.科学技術の問題点 | |
| DDT(合成殺虫剤)は節足動物に対しては非常に有効であるが、哺乳類に対しては比較的無害であった。1939年スイスのポール・ミュラーが人畜無害の殺虫剤を開発した。マラリア蚊の減少に大変寄与し、1948年にノーベル医学生理学賞を受賞した。しかし、1962年レイチェル・カーソンが「沈黙の春」でDDTやDHC始めとする塩素を含んだ殺虫剤や他の科学物質に対する環境の汚染の実態を描いたことで、その後DDTが全面禁止となった。 原子核分裂の発見とその利用ではアインシュタインが1922年ノーベル物理学賞を受賞した。とりわけ光電子効果の法則の発見がきっかけとなった。1906年原子核が発見され1932年実験で確認、1939年核分裂とその連鎖反応が発見された。マンハッタン計画で核分裂が兵器として開発された。アインシュタインがルーズベルト大統領に手紙を書き、アメリカがドイツに先んじて原爆を開発することとなる。1941年ウラン型原子爆弾の開発、1945年7月16日に初の原爆実験が行われた。同年8月6日広島にウラン型原子爆弾が投下された。 |
|
| 5.21世紀は知の世界 | |
| 20世紀は「科学技術の世紀」であり21世紀は「知の世紀」になってほしいと、多くの人は願っている。 知と言うとそれを応用して役に立つ「実用の知」と心が豊かになる「精神の知」というものがある。 「実用の知」ばかりを追うと「精神の知」を生み出す人文科学・社会科学は社会的な効用がないと、軽視されるおそれがある。自然科学の発展は人文科学・社会科学相携えて、技術者は科学技術の両面性を認識した上で「社会のための社会の中の科学技術」という観点に立つ必要がある。 「科学技術」と「社会」は緊密な関係の上に成り立っている。また科学技術者は「社会」から研究支援を必要とし、社会と人類に対する研究の自覚と高い倫理観が求められる。「科学技術」と「社会」との関わりを大切にする必要がある、ということだ。 内閣府が行った科学技術と社会に関する世論調査を見ると、科学的研究は人類に新たな知識をもたらすという意味では不可欠であると思われる人の数は70%程度ある。また、科学技術はプラス面があると考えている人の数も多く、60%に達する。科学技術の発展により、社会生活の安全性については疑問符があるものの物の豊かさ、健康を守り生活の楽しみや労働条件の向上をあげる人が多く、物質的な豊かさばかりでなく、心を豊かにしてくれると感じる人が半数を超え7割・8割に近いことがわかる。 しかし、科学・技術者に親しみを感じていない人は70%を越え、科学・技術のニュース・話題への関心の度合いははっきりと「ある」「ない」の分極化が進んでいる。科学技術を社会との関わりにおいて考える必要性・重要性を指摘しているデータとなっている。 |
|
| 6.今後の課題 | |
| わが国の科学技術政策の骨組みは、昭和34年科学技術会議が設置され、長期・総合的な研究目標の設定を目的としたが活発な活動は行われなかった。そこで、平成7年科学技術と社会の調和をはかるための科学技術基本法が制定され、翌年から5年計画の第1期科学技術基本計画が策定された。平成13年人文社会科学も含み倫理問題等の社会や人間との関係を重視した総合科学技術会議が設置され、第2期科学技術基本計画がスタートした。それにより、研究者の数はここ数年頭打ちではあるが、研究費の総額は16兆円を超え、世界で2番目の金額となった。また、基礎研究を支える科学研究費補助金も増加し、それに併せてノーベル受賞者を輩出している。しかし、受賞対象の研究・実験を開始したのは必ずしも研究費増加後ではなく、わずかな金額での研究が受賞に結びついている現実もある。また、基礎的・基盤的な研究成果の評価には時間がかかることも併せて考えると、人文科学・社会科学も含めての知的創造的活動拠点の大学のありようが今後の課題となってくる。 考える材料として言うと、1960年代に大学紛争が吹き荒れた。 大学の大衆化の批判と大学制度全般の批判が「象牙の塔」に象徴されている。 |
|
| 7.おわりに | |
| 大学は社会に開かれていなければならない。個性的な独創性と人間の形成、人類の知的資産の拡充など、開かれた「象牙の塔」にならなければならない。学部における教養教育、複数選考の教育(自然科学と人文・社会科学の交流)のシステムにする必要がある。理系と文系の交流にもなる。 高校レベル言えば、文系・理系のくくりはやめてほしい。初等中等教育の20人学級の早期実現と、いかに個性的な教育ができるかどうかが重要となる。知識だけでなく自分なりに考え、自分の意見を主張できるような人格を目指す教育が必要である。それには、子供を育てる両親への教育−社会人教育が必要であり、知識偏重を廃し、自然に親しむことを主眼とした幼児教育が必要である。 司馬遼太郎氏は「高い童心を持て。大人は子供の持っている疑問を持たなくなる。その疑問を忘れたところから大人になる。子供は好奇心の固まりである。」と言っている。 自然科学者で難病のため研究者としての活動を休止せざるをえなくなった、柳澤桂子氏は「女子高校生のための生命科学の本」の序の結びで「もしあなたに赤ちゃんが生まれたならきっとびっくりする、子供の質問には一生懸命答えてあげて下さい。子供は好奇心を持つことを楽しみにしている。好奇心失わないで豊かに生きて下さることをお祈りします。」と述べている。童心を、好奇心を、忘れないでもらいたい。 |
|
| 8.会場での質疑 | |
| Q1 「先生は、科学は自然と共存するための知識を得るものだとおっしゃったのですが、今の科学は自然と共存するための知識を得るための方向で進められていますか。」 |
|
| A1 「全面的そうであるとは言えないが、かなりの部分はそうである。」 |
|
| Q2 「科学はこれからどんなことを研究・勉強して自然と共存していくと思いますか。」 |
|
| A2 「全体の趨勢とういうのは自分の意見とは違うかも知れないが、健康で長生きをしたいという意味で、バイオテクノロジーを利用したいろんな新しい薬を作る、あるいは新しい医療方法を開発するといった研究が進むだろうと思います。 私の個人的な希望は、どこの国でも不足するのが、エネルギーと水であるので、それをどうするのかという研究だ。エネルギーで言えば、原子力に頼るか、化石燃料に頼るか、いずれにしても次世代につけを回さなければならない。究極は太陽光で、太陽光をどう利用するか、太陽電池、あるいは生物を使った太陽電池、植物が行っている光合成を科学的にやって、でんぷん・タンパク質に変換できればエネルギー不足に対応できるのではないか。エネルギー不足、水不足に対応する科学技術の発展を願っている。」 |
|
| Q3 「先生の開発された導電性高分子の今後の社会における期待を教えて下さい。」 |
|
| A3 「導電性高分子は、金属しか電気が流れないと思われていたことと、プラスティックには電気が流れないと思われていたことを覆す非常に画期的な発見であった。 プラスティックは事前に形を変えられる、柔軟性があるとか、いろんな性質があり、応用範囲が広い。発表と同時に多くの企業が興味を持った。 実用化が一番近いと思われるのがバッテリー。自動車に現在搭載されている鉛電池の容量の大きいものが望まれている。コンデンサーの部品にはすでに使われており、携帯電話やテレビにいくつか入っている。蛍光発光を使ったフルカラーのディスプレイが実用化されるよう研究されている。また、スクリーンくい応用、ドーピングセンサー、味覚センサー、人工筋肉使うような研究もされている。分子素子を作るというような応用もある。」 |
|